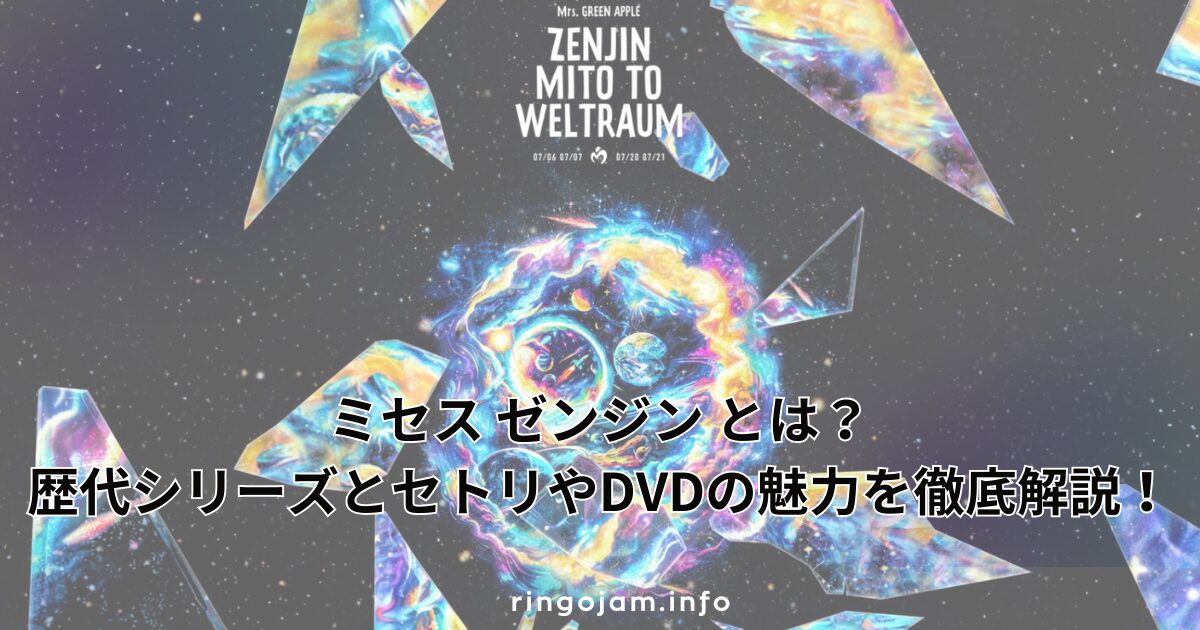「ミセス ゼンジン とは?歴代シリーズとセトリやDVDの魅力を徹底解説!」というテーマでお届けします。
「ミセス ゼンジン未到って何?」「シリーズごとの違いや見どころが知りたい」「ライブのセトリや円盤・グッズ情報も気になる…」
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
私自身、JAM’S歴5年のファンとしてライブに参加したり、Blu-rayや雑誌で歴代のゼンジン未到を追いかけてきました。
だからこそ、体験談や調べてきた情報を交えて、初心者の方にもわかりやすくまとめています。
この記事では、ゼンジン未到シリーズの意味や歴史、歴代公演の一覧やセトリ、さらにはDVDやグッズの魅力までたっぷり紹介します。
これを読めば、ゼンジン未到シリーズがなぜ特別でファンに愛されているのか、そしてDVDやグッズの選び方まで理解できるはずです。
※この記事は2025年8月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。
ミセス ゼンジン とは?歴史・由来・シリーズ全体像
ミセスファンの間で“伝説的”と称されるゼンジン未到シリーズですが、実はその歴史や意味を詳しく知っている人は意外と少ないかもしれません。
ここでは、ゼンジン未到シリーズのルーツや、バンドの成長とともにどんな風に進化してきたのかを、ファン目線でやさしく解説していきます。
ミセス ゼンジン未到シリーズとは
ゼンジン未到シリーズとは、Mrs. GREEN APPLEがバンド結成初期から行っている自主企画ライブのことです。
「ゼンジン未到」というタイトルには、“前人未到”――つまり「誰も踏み入れたことのない場所へ自分たちで進んでいく」という、バンドとしての強い意思が込められています。
このライブは、2014年に始まり、もともとはライブハウスなどの小規模な会場からスタートしました。
インディーズ時代から続くこのシリーズは、メンバーの加入や脱退、メジャーデビューなど、バンドのターニングポイントで必ず開催される特別なイベント。
他の大型ツアーやコンセプトライブとは違い、ゼンジン未到シリーズは「バンドの“今”」をそのまま表現する場として、ファンからも非常に愛されています。
ゼンジン未到シリーズの特徴
- バンド自身が“原点回帰”するタイミングで開催される
- ストーリー性よりも“今のミセス”をそのまま体感できる
- セトリや演出も自由度が高く、その時の気分や挑戦が盛り込まれる
たとえば、「ゼンジン未到とコンフリクト〜前奏編〜」ではベースの脱退発表、「ゼンジン未到とプログレス〜実戦編〜」ではメジャーデビュー発表があり、どれもファンの記憶に残る重要な場面となっています。
ゼンジン未到シリーズ 一覧とそれぞれの特徴
ここで、ゼンジン未到シリーズの歴代ライブを一覧でまとめます。
それぞれの公演にはバンドの成長や時代背景が反映されていて、「ミセスの物語」を感じることができます。
| 開催年 | タイトル | 会場 | 主な出来事・特徴 |
|---|---|---|---|
| 2014 | ゼンジン未到とコンフリクト〜前奏編〜 | 渋谷LUSH | 初の自主企画/ベース松尾拓海の脱退発表/2nd会場限定CD『Introduction』発売 |
| 2014 | ゼンジン未到とパラダイムシフト〜音楽編〜 | 新宿MARZ | 新ベース高野清宗の加入発表/サポート森夏彦参加/観客200人規模 |
| 2015 | ゼンジン未到とプログレス〜実戦編〜 | 新代田FEVER | メジャーデビュー発表/2枚目ミニアルバム『Progressive』リリース直後 |
| 2017 | ゼンジン未到とロワジール〜大阪/東京編〜 | 大阪野音/日比谷野音 | デビュー2周年記念/初の野外ワンマンライブ/シャボン玉・水鉄砲演出 |
| 2018 | ゼンジン未到とプロテスト〜回帰編〜 | 全国ライブハウス | 結成5周年/原点回帰/ミニマルな演出と照明/渋谷CLUB CRAWLでファイナル |
| 2022 | ゼンジン未到とリライアンス〜復誦編〜 | 全国Zeppツアー | フェーズ2開幕/初のZeppツアー/“諳んじる(復誦)”=再確認・新章突入 |
| 2024 | ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜 | 全国スタジアム | 史上最年少でスタジアムツアー開催/「宇宙×個」のテーマ/初の映像円盤化 |
どの公演も、その時のMrs. GREEN APPLEの「現在地」を感じられるものばかり。
ファンにとっては「バンドと一緒に歩んできた時間」を感じさせる大切なシリーズです。
ゼンジン未到とリライアンス 復誦編とは?
ゼンジン未到とリライアンス〜復誦編〜は、バンドの“第二章”の幕開けともいえる公演です。
活動再開後、フェーズ2として初めて開催され、Zeppツアーとして全国14公演が行われました。
この復誦編の特徴は、シリーズ名に“リライアンス(信頼)”と“復誦(繰り返し唱える)”という意味が込められていること。
「今までの自分たちの音楽をもう一度見直す」「原点の自分たちに立ち返る」という強い想いがライブの随所に表れていました。
見どころポイント
- 全国Zeppツアーとして、より多くのファンと距離が近い空間を作った
- セトリも各地で変化し、その時のバンドの“等身大”を楽しめた
- ドキュメンタリーや裏側映像もBlu-rayなどに収録され、ファン必見
このライブがあったからこそ、2024年の「ヴェルトラウム〜銘銘編〜」の大規模なスタジアム開催が生まれたといっても過言ではありません。
ミセス ゼンジン未到シリーズの見どころ・楽しみ方まとめ
ここからは、ファンなら誰もが気になるゼンジン未到シリーズの「ライブの中身」や「映像・グッズ情報」について、具体例やセットリストを交えながら紹介します。
ミセス ゼンジン未到 セトリとライブ演出の魅力
ゼンジン未到シリーズといえば、その時々の「ライブでしか味わえない空気感」が魅力です。
毎回、代表曲からレア曲、さらにサプライズ曲まで、今のミセスを体現するセットリストが組まれます。
2024年スタジアムツアー(ヴェルトラウム〜銘銘編〜)の例
※MCやサプライズ演出も盛りだくさんで、「Magic」では撮影OKという新しい試みも。
| 曲順 | 曲名 | 特徴・演出 |
|---|---|---|
| 1 | CHEERS | 開幕から「乾杯!」で全員参加の祝祭感 |
| 2 | VIP | ファン全員が「嫌い!」と叫ぶ定番シーン |
| 3 | ANTENNA | サビで会場が一体化、照明演出も華やか |
| 4 | ロマンチシズム | 青春感あふれるミセス定番曲 |
| 5 | ツキマシテハ | 大森の荒々しいボーカルが際立つライブ映え曲 |
| 6 | CONFLICT | ゼンジンシリーズの象徴曲、深い歌詞が胸を打つ |
| 7 | 青と夏 | 夏の定番ソング、会場全体が実家のような安心感に包まれる |
| 8 | ライラック | 青と夏のアンサーソング、ひろぱのギターが印象的 |
| 9 | 橙 | 日没の時間に合わせてスタジアムがオレンジに染まる |
| 10 | 点描の唄(ソロ) | 大森のソロでしっとり聴かせる、感情が震える瞬間 |
| 11 | Blizzard | 涼ちゃんの煽り「3,2,1 GO!」が印象的 |
| 12 | インフェルノ | 炎の特効演出が加わり、熱気が最高潮に |
| 13 | 私は最強 | 劇場版ワンピース曲、会場が一気にぶち上がる |
| 14 | Loneliness | 夜空に映えるアレンジ、ダークでエモーショナル |
| 15 | アポロドロス | ファン参加型の盛り上がり曲、公式映像も公開された |
| 16 | L.P | 意表を突く選曲、歌詞が胸に刺さる |
| 17 | ナハトムジーク | “夜の音楽”の意味を持つ曲、静寂とともに始まる感動的瞬間 |
| 18 | コロンブス | 3人で肩を並べて演奏、歓声と拍手が会場を包む |
| 19 | Magic(撮影OK) | SNS拡散可能な特別演出、夏のアンセム曲 |
| 20 | Dear | 「ここに記す 貴方へ」で締め、本編を感動的に終える |
| EN1 | Familie | メンバーとファンをつなぐ温かい曲 |
| EN2 | lovin’ | ポップで明るい雰囲気に切り替える |
| EN3 | ダンスホール | 会場総立ちのダンスパート |
| EN4 | 愛情と矛先 | 切実で力強い歌詞が響き渡る |
| EN5 | 我逢人 | ゼンジンの象徴的楽曲として終盤に配置 |
| EN6 | ケセラセラ | 会場全体が大合唱、笑顔で幕を閉じる |
名場面・ファンの声
- 会場のライトが曲ごとに色を変えたり、夏空や夕焼けとリンクする演出が印象的
- 「橙」ではスタジアムがオレンジ色に染まり、季節感と一体感がMAXに
- メンバーのビジュアルチェンジ(髪色、衣装、カラコンなど)やサプライズ企画もあり、毎回新しい発見がある
このように、「その瞬間しか体験できない」特別なライブ空間をつくり上げるのが、ゼンジン未到シリーズならではの魅力です。
ミセス ゼンジン未到 dvd&グッズ情報【映像作品・限定アイテムのおすすめポイント】
ミセスのライブの熱狂や感動は、Blu-rayやDVDでも余すことなく楽しめます。
特にゼンジン未到シリーズは、近年になってついに映像円盤化され、ファンの間で「待望」の声が多く上がりました。
代表的な映像作品と限定グッズ一覧
| タイトル | 映像収録・特典内容 | グッズ例 |
|---|---|---|
| ゼンジン未到とロワジール(2017) | アルバム『ENSEMBLE』やシングル『Love me, Love you』初回盤の特典映像 | オリジナルポーチ/クリアカード等 |
| ゼンジン未到とプロテスト〜回帰編〜 | ライブ映像・ドキュメント収録 | フォトカードセット/限定タオル |
| ゼンジン未到とリライアンス〜復誦編〜 | ドキュメンタリー映像『ANTENNA』初回限定盤 | バンドロゴグッズ/公式アパレル |
| ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜 | 初のBlu-ray/DVDフルパッケージ化(特設サイトで発売) | LPサイズフォトブック/トート/ガジェットケース等 |
グッズのおすすめポイント
- LPサイズスクエアフォトブック(44P)、フォトカードセット、MIXトートバッグ、トラベルポーチ、ガジェットケース、SNS風クリアカード、フレークステッカー、シュシュなど、ライブ映像と合わせて“コレクション性”も抜群
- Blu-ray&DVDパッケージは特設サイトや一部ショップ限定の特典付きで販売され、完売も続出
ライブに参加できなかった方も、Blu-rayやグッズで“あの日の熱狂”を何度も楽しめるのがこのシリーズの醍醐味です。
ミセス ライブ 歴代セトリとゼンジン未到シリーズの違いを解説
ゼンジン未到シリーズと他のミセスライブ(ツアーや単発公演)には、実は大きな違いがあります。
ここでは、歴代セトリやライブごとの雰囲気を比べてみます。
ゼンジン未到シリーズと他ライブの違い
| 項目 | ゼンジン未到シリーズ | 通常ツアー・単発ライブ |
|---|---|---|
| 開催タイミング | バンドの節目や新章スタート時 | アルバムリリースや大型フェス |
| 会場規模 | 小規模ライブハウス→スタジアムまで幅広く | 主にアリーナやホールなど大型会場 |
| セットリスト | レア曲や実験的な演出、未発表曲も登場 | 新曲+代表曲が中心、安定の盛り上がり |
| ファンとの距離感 | 一体感が強く、MCやサプライズも多い | プロダクション演出や照明が華やか |
| 映像・円盤化 | 限定盤や特典映像が多く、ファンアイテム性高い | 通常盤/大手ショップで流通する円盤が多い |
歴代セトリや代表曲
- ゼンジン未到シリーズでは「CONFLICT」「我逢人」「Magic」「橙」など、その時期のミセス“らしさ”を詰め込んだ選曲が多い
- 通常ツアーでは「青と夏」「インフェルノ」「ダンスホール」など人気曲・代表曲が安定して組み込まれる
このように、ゼンジン未到シリーズは「一回限りの特別な体験」を重視したライブ。
“今のミセスを一番近くで体感したい!”というファンには絶対に外せないイベントです。
ファンの声から見るゼンジン未到の魅力
ゼンジン未到シリーズは、公式発表だけでなく実際に参加したファンの声からもその魅力がよく分かります。
ここでは第三者のレビューや参加レポートを引用し、よりリアルな体験談をご紹介します。
SNSやブログでの体験談
- 「神戸公演に参加しましたが、初っ端の『CHEERS』から会場全体で乾杯する雰囲気が最高でした。」
「演出に頼らずともバンドの演奏力で圧倒された」
(2024年7月・noteユーザー「のーりん」さんの投稿より →記事 リンク) - 「バンド感溢れるパワフルな内容だった。照明や演出も良かったけど、それ以上に“音”がしっかり届いたのが嬉しかった」
(2024年5月・Amebaブログ「emi-1308」さんの参戦レポより→記事リンク)
音楽メディアによるレビュー
- 「ゼンジンは演奏の筋力を試される場だ。観客が見たいのは派手な演出ではなく、バンドそのものが鳴らす音」
(2024.08.06 公開BARKSレビューより→記事リンク)
セットリストを振り返る声
- 「26曲という大ボリュームの中に『CONFLICT』『我逢人』『Magic』など歴代を象徴する楽曲が組み込まれていて、ファンの期待に応える構成だった」
(Awesomemagazine公式まとめより→記事リンク)
ファンの声でわかるゼンジン未到の魅力
- 演出に頼らずとも「演奏そのもの」が感動を生むライブ
- 過去と現在をつなぐ象徴的な楽曲がセトリに散りばめられている
- 初心者でも「CHEERS」「青と夏」「Magic」などで一体感を味わえる
こうした参加者やメディアの声は、ゼンジン未到シリーズが“ただのライブ”ではなく「ファンと一緒に進化してきた特別な場」であることを証明しています。
まとめ
「ミセス ゼンジン とは?歴代シリーズとセトリやDVDの魅力を徹底解説!」というテーマでお届けしました。
この記事では、ミセスのゼンジン未到シリーズについて、
- シリーズの成り立ちや意味
- 歴代ライブの特徴やセットリスト
- 魅力的なDVDやグッズ情報
- 他ライブとの違いや楽しみ方
など、ファン目線でわかりやすくご紹介しました。
ゼンジン未到は、Mrs. GREEN APPLEの“今”を感じられる特別なライブ体験。
この記事が、これからゼンジン未到をもっと深く楽しみたい方や、ライブを体感したい方の参考になれば嬉しいです。
情報源の信頼性と第三者目線での記事作りについて
本記事では、公式サイトや大手ニュース、SNS・Q&Aなど多様な情報源から事実や口コミを集め、できる限り客観的にまとめました。
特定の立場に偏ることなく、JAM’Sとしても中立的な第三者目線を心がけています。
信頼性の高いデータや、実際の体験談、運営側の公式コメントも引用し、内容の正確さを重視しています。
今後も情報のアップデートや出典の明記に努め、読者の皆さまが納得して参考にできる記事作りを目指します。
筆者プロフィール
この記事を書いた人:ジャムおじさん(Webライター / JAM’S歴5年)
ファン目線でリアルなレビューと、公式情報を組み合わせて記事を執筆しています。
執筆者情報:プロフィールページ